
【第4回】ハラルの基礎とハラル認証、イスラム教徒マーケット分析【連載記事】
協会からのお知らせメディア掲載情報最新ハラルニュースハラル認証が“いる”ハラルビジネス、“いらない”ハラルビジネス こんにちは、ハラル・ジャパン協会の川本です。さて今回は「ハラル認証が“いる”ハラルビジネス、“いらない”ハラルビジネス」を解説していきます。ハラルビジネスに…

ハラル認証が“いる”ハラルビジネス、“いらない”ハラルビジネス こんにちは、ハラル・ジャパン協会の川本です。さて今回は「ハラル認証が“いる”ハラルビジネス、“いらない”ハラルビジネス」を解説していきます。ハラルビジネスに…

ハラル・ジャパン協会コンサルティングにより、2024年4月1日付けでステーキテンダーロイン銀座がハラル認証(メニュー認証)を取得されました。 ステーキテンダーロイン銀座は、東京の銀座にあるステ…

東京外国語大学(東京都府中市)で、2024年4月15日(月)〜19日(金)の1週間、ハラール弁当が販売されました。学内の留学生は約680名、その内の約70名がイスラム圏出身です。今回のハラール弁当は、東京ハラルデリ&カフ…

ハラル認証取得の基本を学ぶ【食品ハラルビジネス進化論~ハラル認証原料編】 こんにちは、ハラル・ジャパン協会の川本です。最近はインドネシアをはじめ、マレーシア、シンガポールに向けの輸出を検討したいという声やお問い合わせをた…

GCC6か国は、 サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、クウェート、オマーン、バーレーンなど6か国から構成されています。 いままで中東の窓口としてはアラブ首長国連邦があるドバイやアブダビが注目され人気でした、今も大…

03月29日に発表されたJETROのハラール認証に関する最新の調査レポートです。 これからイスラム市場に進出を考えている。またはハラール認証の取得を目指す日本企業はとても参考になりますので是非、ご覧ください。  …

ハラル・ジャパン協会とインドネシアのハラル研修機関「Halal Institute」がコラボレーション開始! インドネシア (ジャカルタ) — 日本のハラルビジネス業界のパイオニア、一般社団法人ハラル・ジャパ…
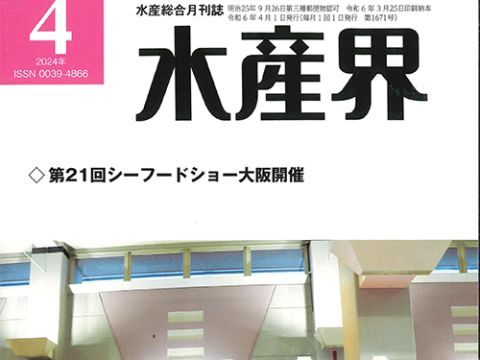
大日本水産会の会報誌「水産会」4月号にハラル・ジャパン協会が掲載されました。是非、ご覧ください。 ⇒水産界4月号DHAマリンフーズ

発酵食品の世界的なポテンシャルと地域経済にもたらす波及効果を知ることができる ハラル・ジャパン協会と業務提携をしている(一般)アジアフードビジネス協会からのセミナーのご案内です。 業界を牽引してきたマルコメ株式会社代表取…

株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営するブランチ カフェ「FLIPPER’S」は、渋谷店と下北沢店にてムスリムフレンドリー認証を取得しました。 ⇒「ムスリムフレンドリー認証」を取得…




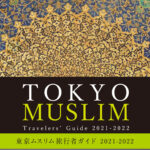






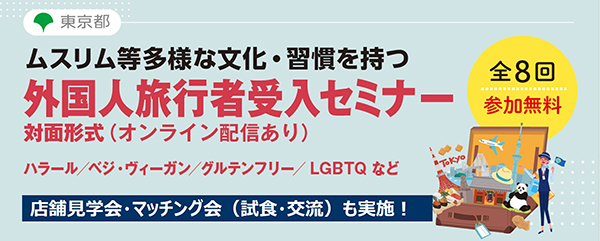


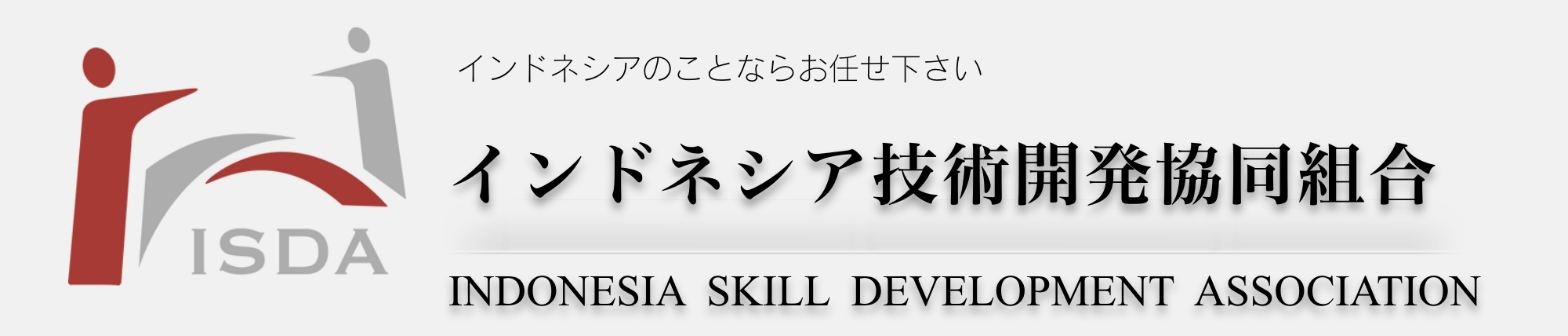

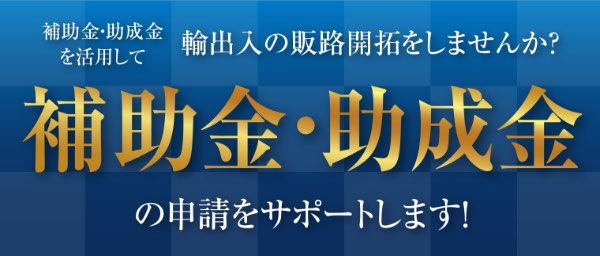

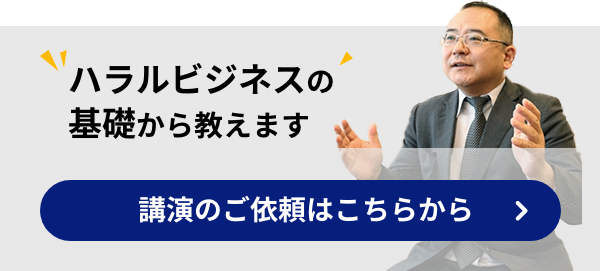
全国各地域でのハラルビジネスの普及と包括的なサポートを目的とし、地銀18社様と業務提携をしています。
